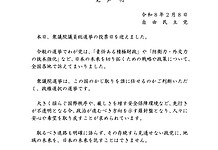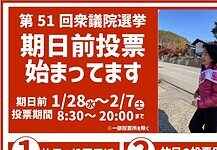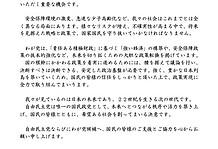【食品ロス削減の推進に関する基本的な方針の変更】閣議決定と今後の取り組み
【食品ロス削減の推進に関する基本的な方針の変更】が3月25日(火)に閣議決定されました。
「食品ロス」は、私たちの暮らしに密接に関わる問題です。
令和4年度(2022年度)には、家庭系・事業系それぞれ約236万トン、合計約472万トンの食品が、まだ食べられるにもかかわらず廃棄されました。これは国民一人あたり、おにぎり1個分(約103g)を毎日捨てている計算になります。
限りある資源を守り、環境への負荷を減らすためにも、食品ロスの削減は喫緊の課題です。
関係府省庁連絡会議の座長としての取り組み
私は、2022年6月より「食品ロス削減に関する関係府省庁連絡会議」の座長を務め、関係省庁とともに制度の見直しや新たな取組の検討を重ねてまいりました。
この度、その取り組みの成果として、今年度中に「食品期限表示の改正ガイドライン」が消費者庁から公表される予定です。
科学的根拠に基づく表示の見直し
このガイドラインでは、食品の「賞味期限」や「消費期限」の表示方法を、科学的根拠に基づき、よりわかりやすく見直します。これにより、消費者が食品の状態を見て適切に判断できるようになり、まだ食べられる食品の無駄な廃棄を減らすことが期待されます。
第2次基本方針と新たな目標
また、同時に「食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針(第2次)」も、今年度中に閣議決定される見込みです。
この基本方針は、第1次基本方針(2019年策定)で掲げた目標「2030年度までに、家庭系・事業系それぞれの食品ロスを2000年度比で半減」の進捗を踏まえた内容です。
2022年度の時点で、事業系食品ロスは目標を8年前倒しで達成しました。これを受けて、第2次方針では新たに60%削減というより高い目標が設定されました。一方、家庭系食品ロスは、あと約20万トンの削減が必要であり、国民一人ひとりの行動変容が重要です。
教育・啓発・地域との連携による施策強化
第2次方針では、こうした課題に対応するため、具体的な施策が強化されています。
たとえば、教育・啓発分野では、「食の環(わ)プロジェクト」として国の取り組みを一元的に発信するとともに、外食時の「食べ残し持ち帰り」について、消費者の自己責任を前提とした周知が進められます。
また、脱炭素につながる新しい暮らしを提案する「デコ活」や、飲食店などでのmottECO(モッテコ)の普及も後押しされます。
地方自治体の取り組みを広げるため、各地の施策状況を見える化するとともに、食品ロス削減推進サポーターの育成も始まります。さらに、保育所や幼稚園での栄養士・管理栄養士等の配置を通じて、未就学児への食育も強化されます。国際的な連携にも力を入れ、海外の先進事例の共有や展開も視野に入れています。
事業者への支援と制度整備
食品関連事業者に対しては、納品期限や賞味期限の設定方法の見直し、商慣習の改善に取り組むとともに、ICTやAIなどの技術導入による在庫管理や食品寄附の促進など、現場の実効性を高める支援も強化されます。また、企業による食品ロス抑制の取組内容が社会に開示される仕組みの検討も始まっています。
あらゆる主体を巻き込んだ総合的な取り組み
このほか、実態調査や研究の推進、フードバンク団体を通じた未利用食品の寄附活動への支援など、あらゆる主体を巻き込んだ総合的な施策が盛り込まれています。
国民とともに進める身近なアクション
今後も、環境・資源を守り、持続可能な社会を実現するために、国会での議論と現場の声をつなぎながら、着実に政策を前へ進めてまいります。
食品ロスの削減は、家庭でも今日から始められる身近なアクションです。
皆さまとともに、できることから一歩ずつ、取り組んでまいりましょう。
食品ロスに関連する記事一覧